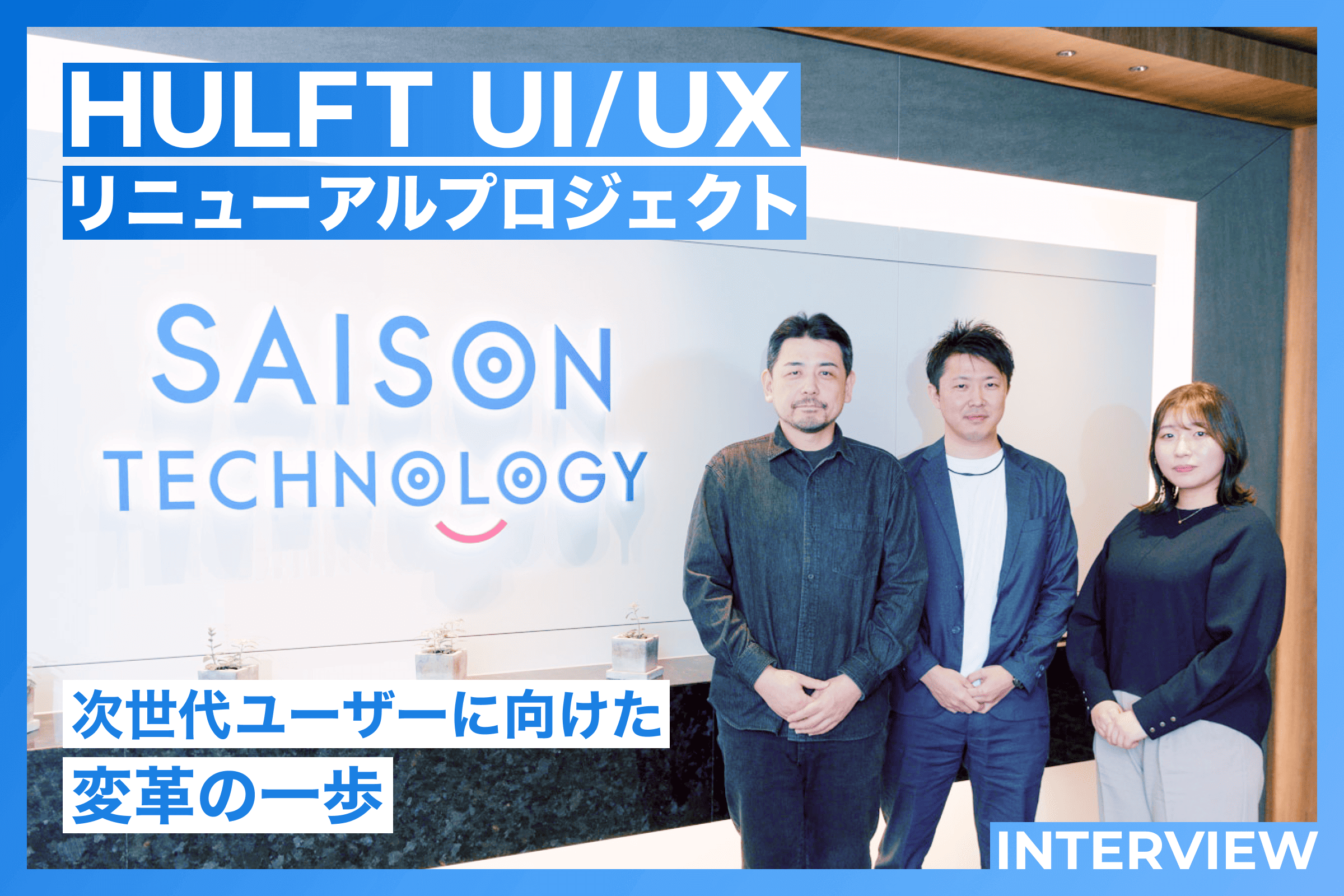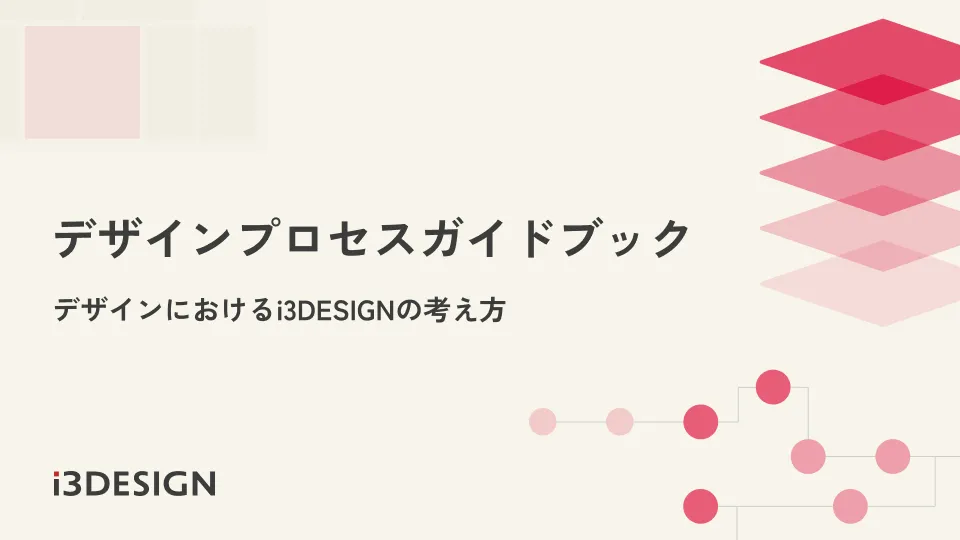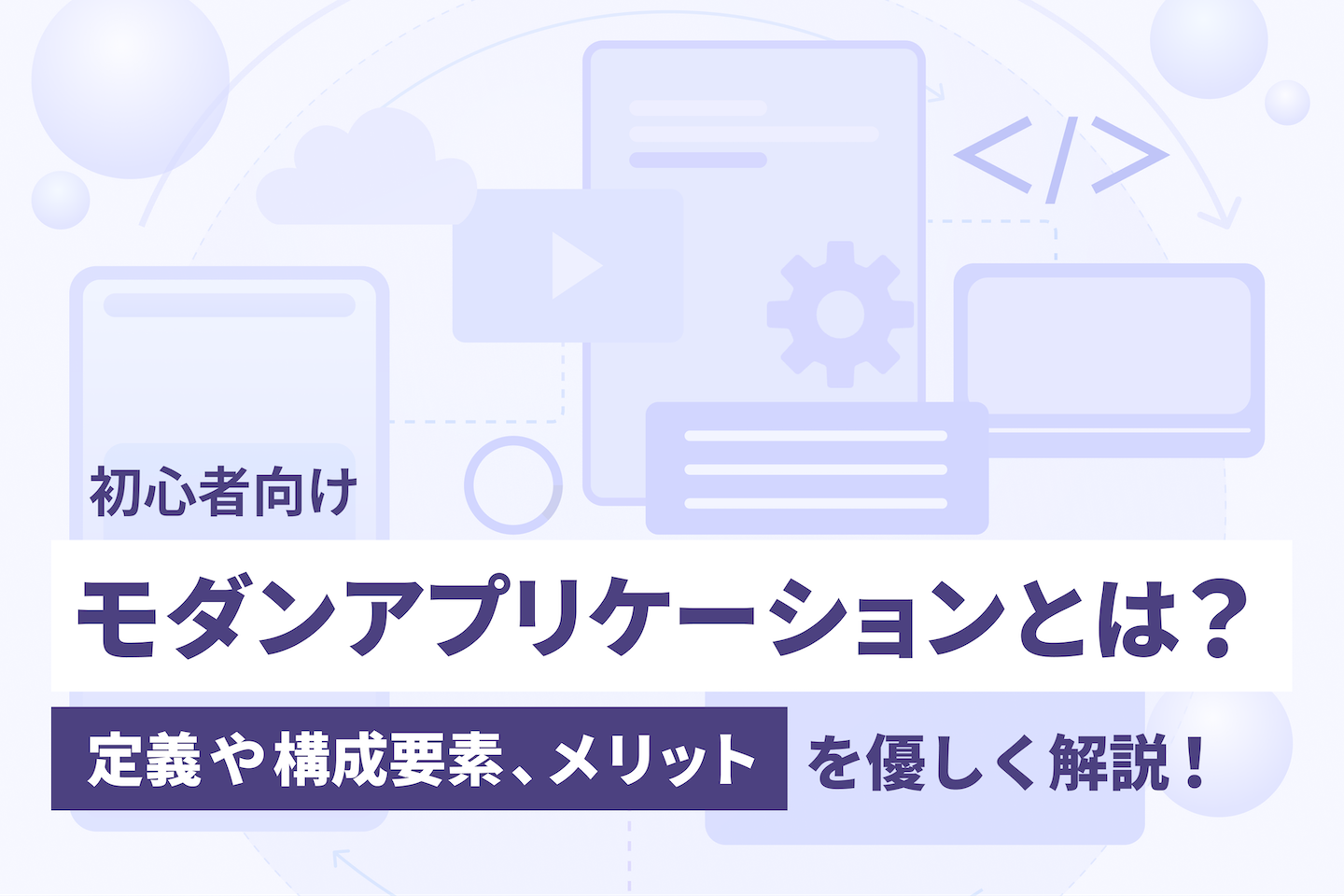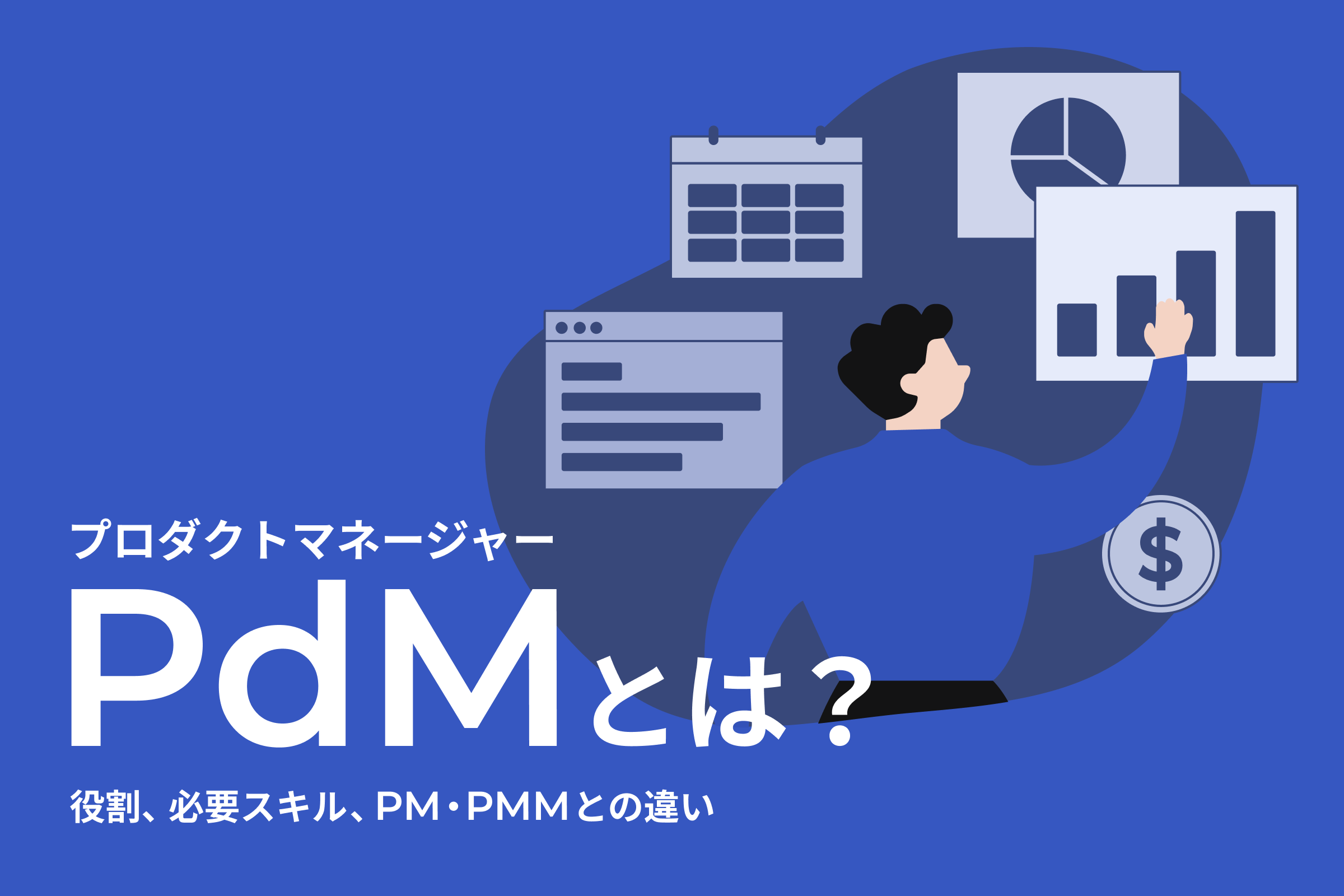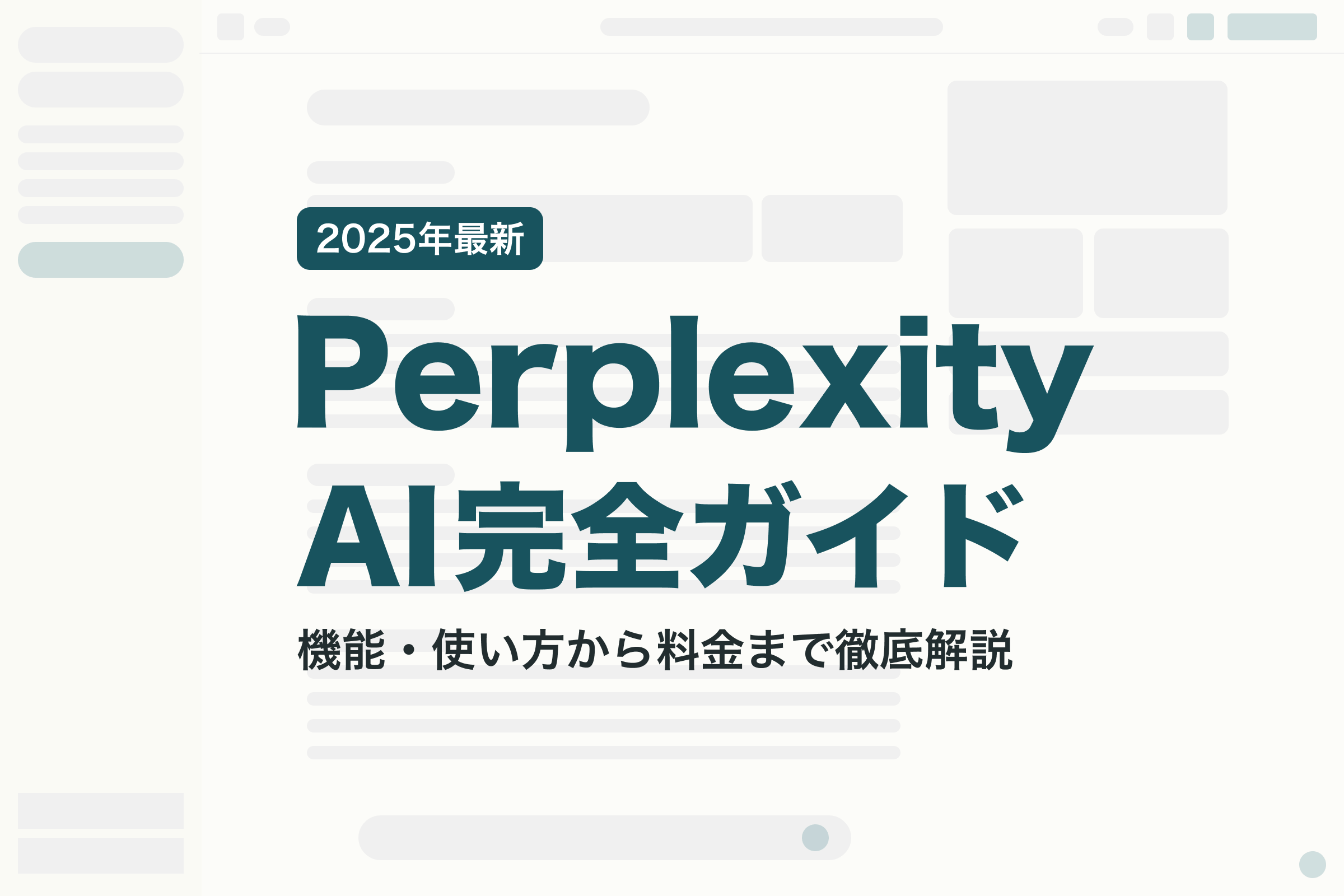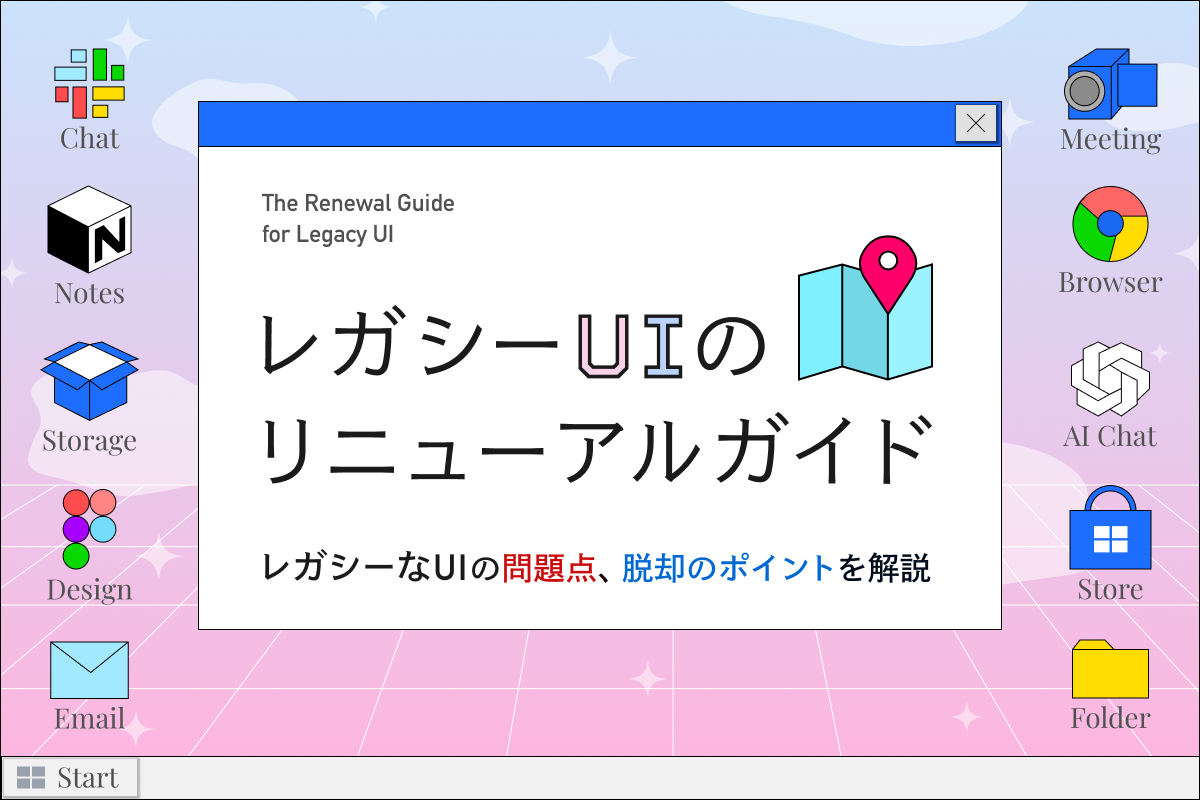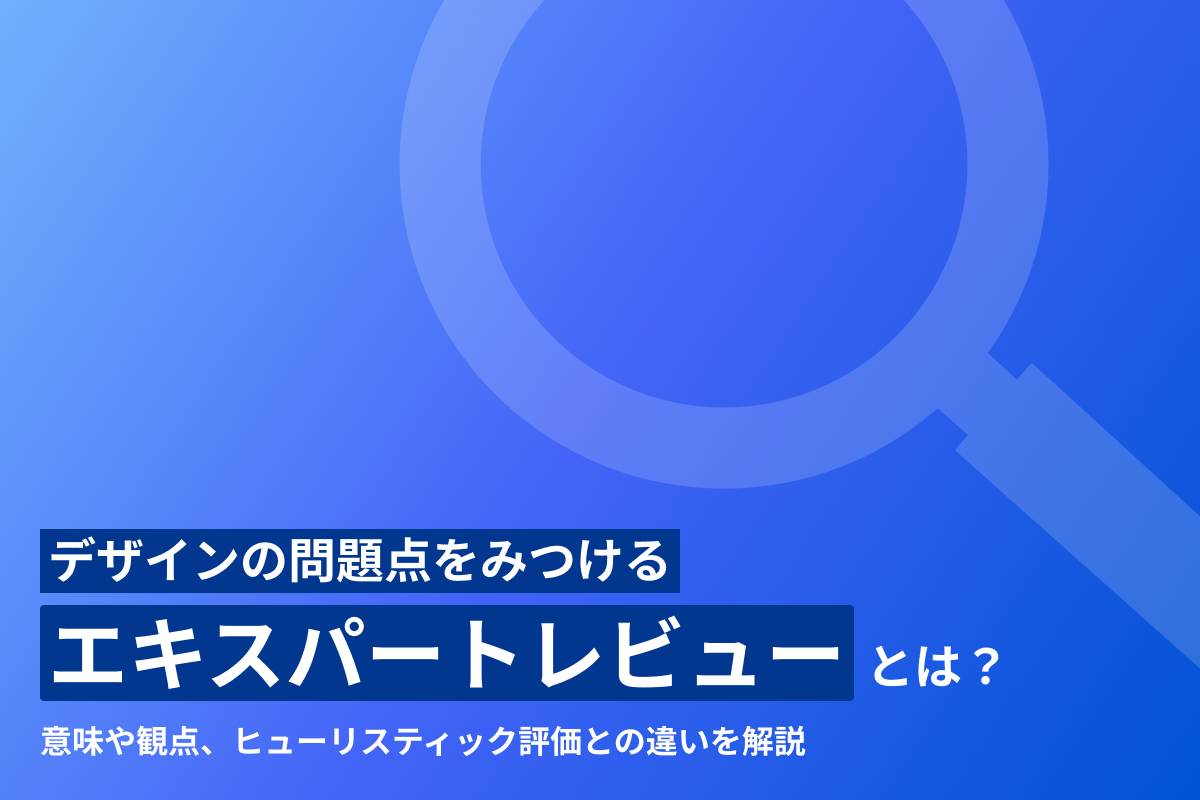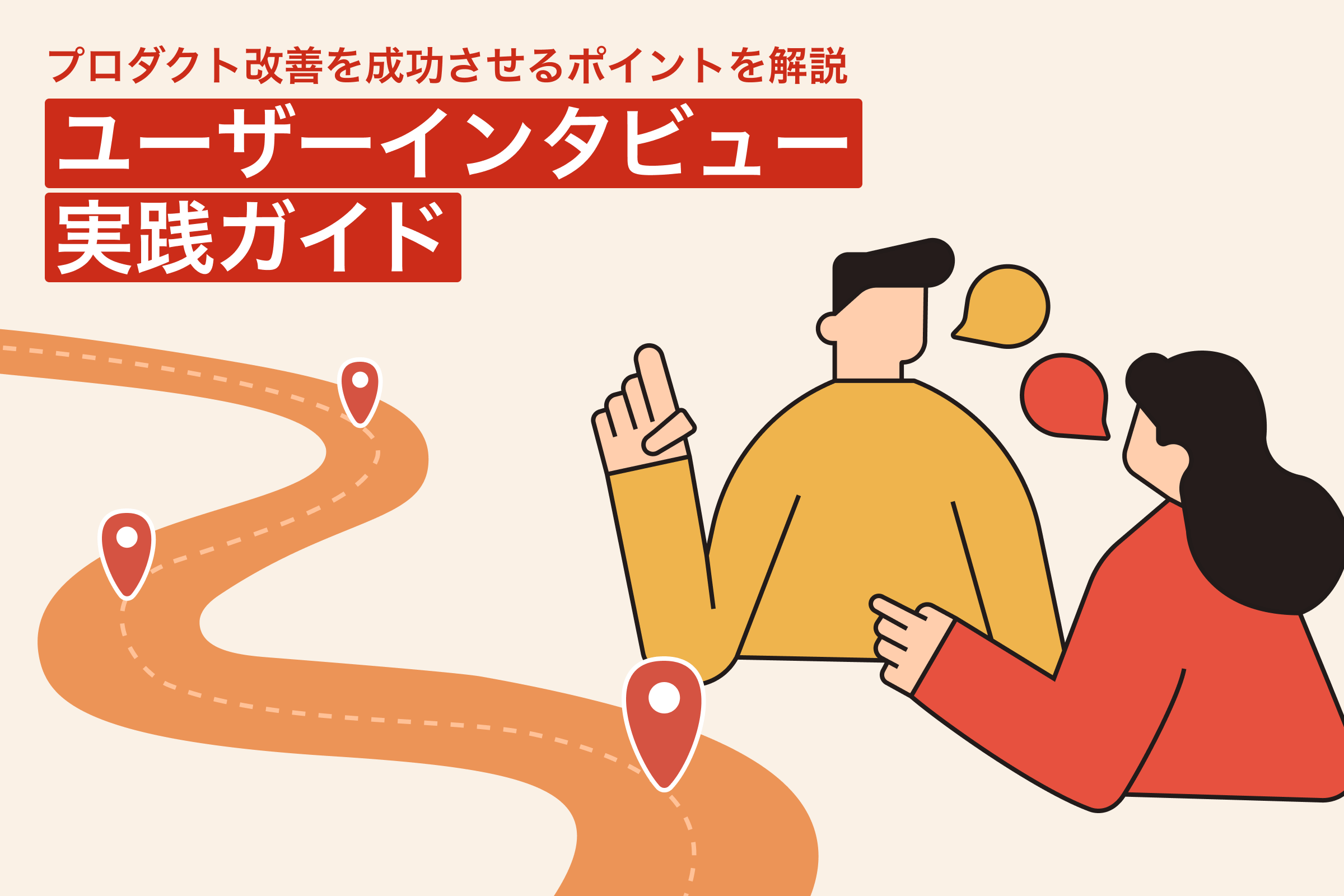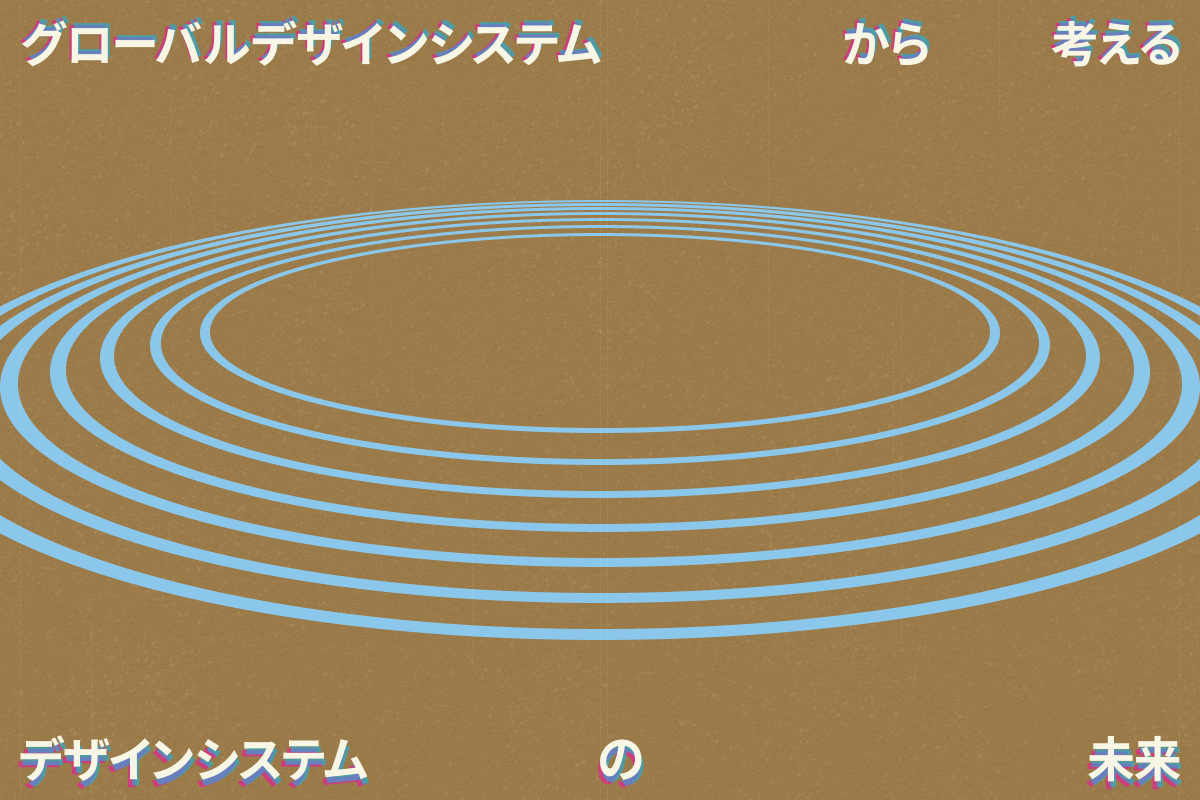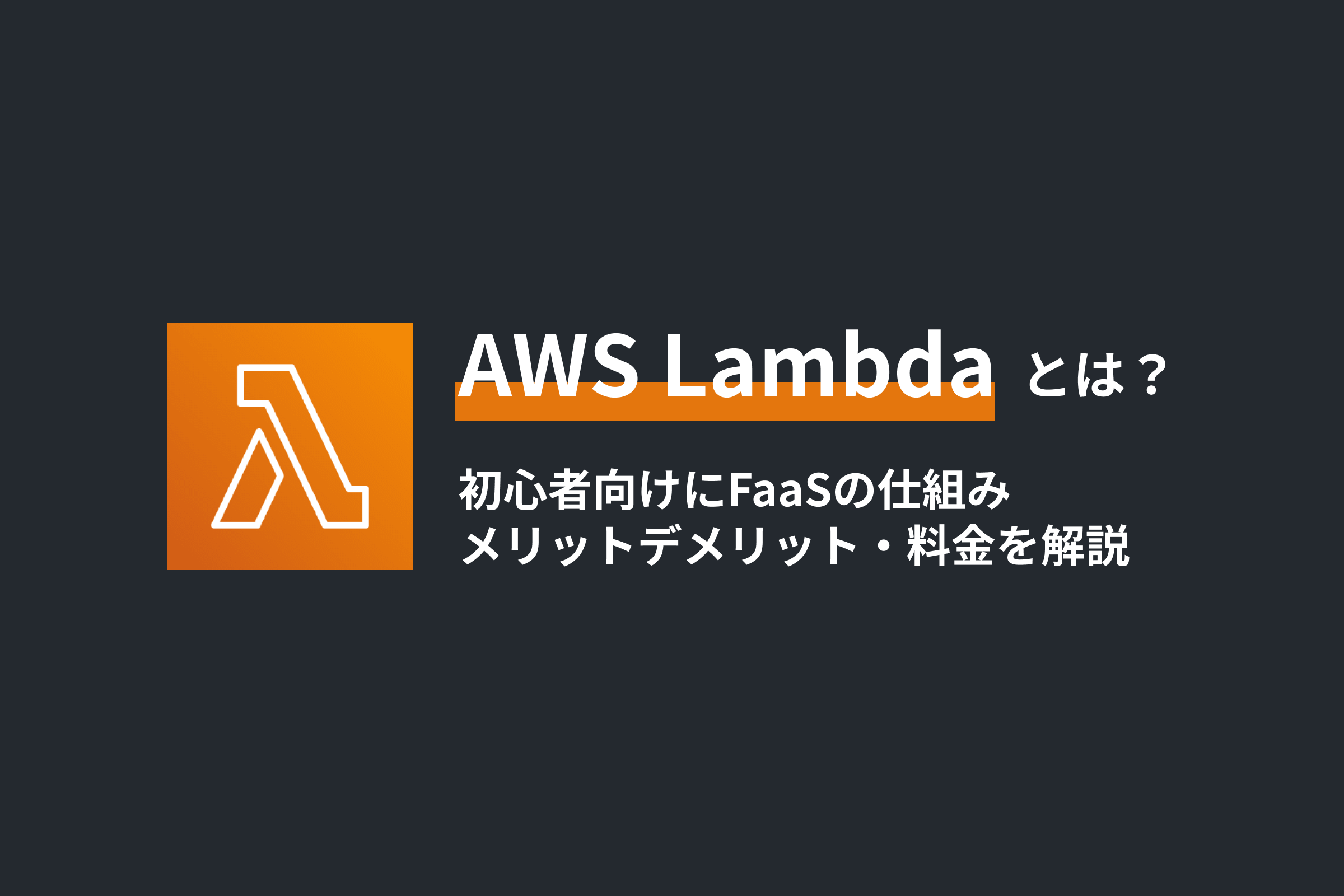国内No.1シェア(*)のファイル転送ミドルウェア「HULFT」。開発元のセゾンテクノロジーでは、次世代のHULFTの開発にむけてユーザーの声を把握し反映させるために、ユーザー調査を十分に行う必要性を感じていました。特に、UI/UXに関して、「長年のユーザーに最適化された現状のデザインが、次世代のユーザーにとって本当に使いやすいのか」という不安がありました。
そこで同社は、HULFT製品群の今後に向けたUI/UXの方針検討に着手。その支援を担ったのがアイスリーデザインです。私たちは、ユーザー調査からUIデザイン、プロトタイプ作成までを担当し、単なるデザインの刷新ではなく、次世代のユーザーが直感的に使いやすいインターフェースとは何かを検証するプロジェクトを進めました。
具体的には、市場調査やNPSアンケート、ヒューリスティクス10原則やUX5段階モデルに基づいたエキスパートレビューを実施。その結果をもとに、以下2つのプロトタイプを作成しました。
- 最低限の改善を施した案
- 大胆に構造を見直した案
これらのプロトタイプと現状の製品画面を用いて、ユーザーインタビューを通じて若年層ユーザーのリアルな反応を検証しました。その結果、現状のデザインに対する課題点が明確になり、次世代に向けたUIの方向性を具体化することができました。
このプロジェクトをきっかけに、HULFTの開発チームのUI/UXに関する知見の強化を目的とした伴走型のプロジェクトも新たにスタート。本記事では、プロジェクトの全体像と具体的な取り組みについて、セゾンテクノロジーの宇佐美さん、真田さん、鹿山さんに、アイスリーデザインの武本、後藤、大林を交えて話を伺いました。

HULFTの豊富な製品群の最新情報やサービス詳細をチェックすることができます。
(*)出典:株式会社富士キメラ総研「2004-2010パッケージソリューションマーケティング便覧」
「ソフトウェアビジネス新市場 2011-2024年版」 <ファイル転送ツール パッケージ・金額ベース>2003年度実績~2023年度実績(2022年度までセゾン情報システムズ実績)
歴史ある製品の次世代に向けた挑戦
—— 今回のプロジェクトは、どのような課題や背景から始まったのでしょうか?
宇佐美さん
HULFTは業界内で寡占状態にあり、現状、お客様からの不満は特に聞こえてきていないものの、長年の歴史がある製品であるため、このままでは「新しい世代には受け入れられないかもしれない」という危機感がありました。そこで、スモールスタートを目指して自部門だけで調査に取り組むことに決めました。しかし、私たちのチームにはそのための専門的なノウハウを持ったプロがおらず、内部だけで進めると「ちょっとした改良止まり」で終わってしまう恐れもあったため、外部の力を借りることにしました。今回のプロジェクトは「思いを形にする」ことがテーマでしたので、打ち合わせの段階からしっかり話を聞いてくれたアイスリーデザインにお願いしました。
エキスパートレビューとプロトタイプ作成で課題を明確化
——本プロジェクトにおいて、最も大きな課題は何でしたか? また、それをどのようにクリアしていったのか教えてください。
武本
HULFTは市場シェア1位(*)で、直近の課題ではなく将来の競争に備えるプロジェクトだったため、イメージが掴みにくく難しさを感じました。他のプロジェクトでは「使いづらい」「シェアが少ない」といった明確な課題がありますが、今回は将来の変化を見据えた高い視点での提案が求められました。そのため、まずは社内の状況や宇佐美さんが感じている課題感、HULFTの市場での立ち位置を深く理解するために、市場調査に時間をかけました。また、ただ要望に応えるだけでなく「将来的なビジョンにどう寄り添えるか」を考えながら、プロトタイプ作成や事前アンケートをはじめ、我々のほうからも積極的に解決策を提案していきました。

鹿山さん
今回一緒にプロジェクトを進める中で、アイスリーデザインさんは単に要望を受け取るのではなく、その背景にある情報や前提条件をしっかりと考えながら進めてくださったのが印象的でした。そのアプローチのおかげで、より本質的な課題に対する提案をしていただけたと感じています。
大林
私は、クライアント側にもデザイナーがいるため、期待を超えられるかの不安が常にありました。そのため、プロジェクト全体において、言語化をかなり意識して臨みました。特にエキスパートレビューでは、根拠を明確に伝えることを意識し、ヒューリスティクス10原則とUX5段階モデルに基づいて評価を行いました。ヒューリスティクス10原則は、人間工学研究者ヤコブ・ニールセンが提唱した基本原則で、現在も有効な指標です。この原則に基づいて、たとえばログインボタンに関して「エラー防止の原則に適っていない」とか、「柔軟性・効率性の担保の原則に反している」というように、明確な根拠を示しながらレポートを作成しました。
真田さん
言語化を意識して進めてくださったおかげで、エキスパートレビューの内容がとても伝わりやすくなっていたと感じます。私たちデザイナーにとっては当たり前のことでも、しっかり言語化することで、他部署に説明する際に新たな気づきを得てもらえる場面が多くありました。「こういう原則から説明しないと伝わらないんだな」と改めて実感しましたね。
——エキスパートレビューやユーザー調査で得た知見を、どのようにプロトタイプに反映したのでしょうか?
大林
プロトタイプの作成は、私と後藤さんで行いました。エキスパートレビューの指摘を反映したA案と、構造自体を見直すB案の2案を作成することになり、差別化するために試行錯誤しました。最終的にA案はベンチマークとして挙がっていたMicrosoft 365を参考にシンプルなデザインに統一。B案は、社員アンケートの結果を反映し、Slack・YouTube・Googleなど若年層に人気のツールを参考に、ポップな色使いやオレンジを基調とし、柔らかい丸みのあるアイコンを採用。従来のダイアログ型設定画面をウィザード形式に変更し、より現代的なUXを意識しました。
宇佐美さん
今回のエキスパートレビューでは、非常に多くの改善提案をいただきました。それらの指摘をもとに作成していただいたプロトタイプを確認した際、自分たちが想定していた方向性と大きなズレがなかったことで、自分たちの考えに改めて自信を持つことができました。また、このレポートが資料として上層部や他部署にも共有しやすい形になったことも、大きな成果だったと感じています。
統一感を意識し、試行錯誤を重ねたアイコンデザイン
——アイコンのデザインでは、2〜3回の修正があったとうかがいました。どのような試行錯誤がありましたか? また、最終的にどのような形に落ち着いたのでしょうか?
宇佐美さん
先に概要を私からお伝えすると、HULFT製品群のアイコン作成を依頼した背景には、製品の統一感に課題がありました。たとえば、製品名に「HULFT」と付くものもあれば、そうでないものもある。そこで、6年前にブランドカラーをオレンジに定め統一感を持たせようとしましたが、HULFT8のロゴはレインボーカラーであり、ブランドカラーとの統一という点において、発展途上でありました。
そこで、HULFT10のリリースを機に、HULFT製品群全体に統一感を持たせるアイコンデザインの見直しを依頼し、統一感を強化することにしました。理想としては、Microsoft OfficeのWord・Excel・PowerPointのように、ひと目でHULFT製品群だと分かるようなデザインにしたいと考えました。

後藤
アイコンの作成は、まず、各社がどのようにデザインの共通性を持たせているかを調査し、特にGoogleなどのカラーや統一感の作り方を参考にしました。日本では、Yahoo!のようにロゴを載せる、マネーフォワードのように独特な曲線を共通要素として使うなど、テキストやシンボルで統一感を持たせる事例が多く、「形は違っても統一感がある」デザインとなるとGAFAのように多くのデザイナーが関わるグローバル企業の事例ばかりだったので、それを短期間で再現するのは大変でした。いくつかの方向性を提案し、ご納得いただけたと思った矢先に、意匠の問題が発生し、再検討を余儀なくされる場面もありました。実例を調査しながら検討を重ね、さらに意匠面での配慮も必要だったため、非常に難易度の高い作業でした。
宇佐美さん
アイコンは、小さなスペースに多くの意味やイメージを詰め込む必要があるため、私たちが抱くイメージをうまく引き出し、それを具体的なデザインに落とし込む作業は、非常に難しかったと思います。ただ、おかげさまで最終的に仕上がったアイコンは本当に素晴らしいものになりました! 矢印を共通のデザイン要素として取り入れ、さらに統一感のあるカラーリングを提案していただいたことで、全体の一貫性がしっかり表現されました。新しい製品が追加されてもこのデザインルールに従えば自然と関連性を出せるだろうと感じています。デザイン面だけでなく、今後の展開を見据えた設計になっていることも含めて、非常に満足しています。
大林
セゾンテクノロジーさんのDataSpider Servistaという全く別のサービスのプロジェクトにも関わらせていただいたんですが、その中で、DataSpider Servistaのアイコンも、私たちが作成したガイドラインに基づいて新たに制作されることになったと伺いました。実際にガイドラインが活用されていると知り、とても嬉しく思います。
アイスリーデザインとの協業がもたらした新たな視点
—— 今回のプロジェクトを振り返って、特に大きな収穫だと感じたことは何でしょうか?
鹿山さん
社内にいると、どうしても既存の枠組みから出られないまま改善を進めることになりがちでした。特に、30年の歴史がある製品は互換性を重視せざるを得ず、「本当はこうしたいけど変えられない」という悩みが常にありました。
そんな中で、アイスリーデザインさんと仕事をしたことで、通常のプロジェクトとは違うアプローチを体験できたと感じています。製品の背景を整理し、4P分析を実施しながら市場の状況を把握し、ユーザーリサーチを通じてUIデザインに落とし込んでいく——まさに「こういうことをやりたかった」と思えるプロセスでした。第三者の視点を取り入れながら、1つひとつ丁寧に整理して進められたのは大きなメリットでした。

真田さん
普段UIやアプリの設計を行っていますが、アイスリーデザインさんとのやり取りを通じて、自分の考え方が大きくズレていないことを確認できたのは大きな収穫でした。「自分の判断は間違っていなかった」と自信を持てた一方で、今まで気づかなかった新しい視点も得られました。特に、エキスパートレビューやワイヤーフレーム設計の議論を通じて、より深い理解が得られ、視野が広がったと感じています。
宇佐美さん
正直、最初は不安が大きかったんです。これまでHULFTではデザインを重視してきたことがなく、社内の共感を得られるのかも分からない状況でした。そんな中、素人同然の私たちが本当に正しい方向に進んでいるのか、大きな不安を抱えながらのスタートでした。
しかし、アイスリーデザインさんから非常に丁寧なアウトプットを提供していただいたことで、これからの指針となるような知見や自信を得られました。今後、私たちがこのアウトプットを基に動き、それに対してお客様が「これまでのままでいい」と100人中100人が言うなら、それが答えになるかもしれません。それでも、まずは新たな一歩を踏み出すことができたことが何より大きいと感じています。
レポートの内容に満足しているのはもちろんですが、それ以上に、このプロジェクトを通じて得た知見や、自信を持って進めるための方向性が見えてきたことが、一番の成果だったと思います。
さいごに
本プロジェクトを通じて見えてきたのは、長い歴史と確固たる地位を持つ製品であっても、次世代のユーザーに向けた変革は避けて通れないという現実です。セゾンテクノロジーのHULFTチームが抱えていた「現状は問題ないが将来的な懸念がある」という状況は、多くの成熟した製品・サービスが直面する共通の課題でもあります。
この記事が、自社プロダクトに対して同じような課題を感じている方の解決のヒントになれば幸いです。
弊社のコーポレートサイトには本プロジェクトの事例を掲載させていただいております。プロジェクトの具体を知りたいという方は、ぜひこちらもご覧ください。
アイスリーデザインではロジカルで納得感のある設計を意識し、モバイルアプリ、SaaSプロダクト、業務アプリケーションやECサイトなど幅広いプロダクトのUI/UXデザインを提供しています。
既存プロダクトのデザイン改修を、まずは現状把握から始めたいという方もお気軽にお問い合わせください。ユーザーインタビューやエキスパートレビューなど、プロジェクトに応じた最適な手法をご提案させていただきます。