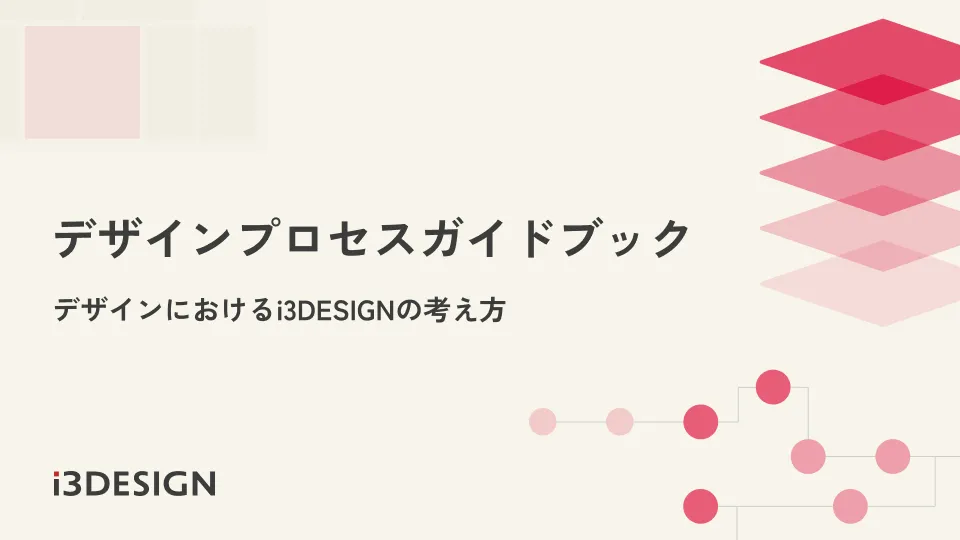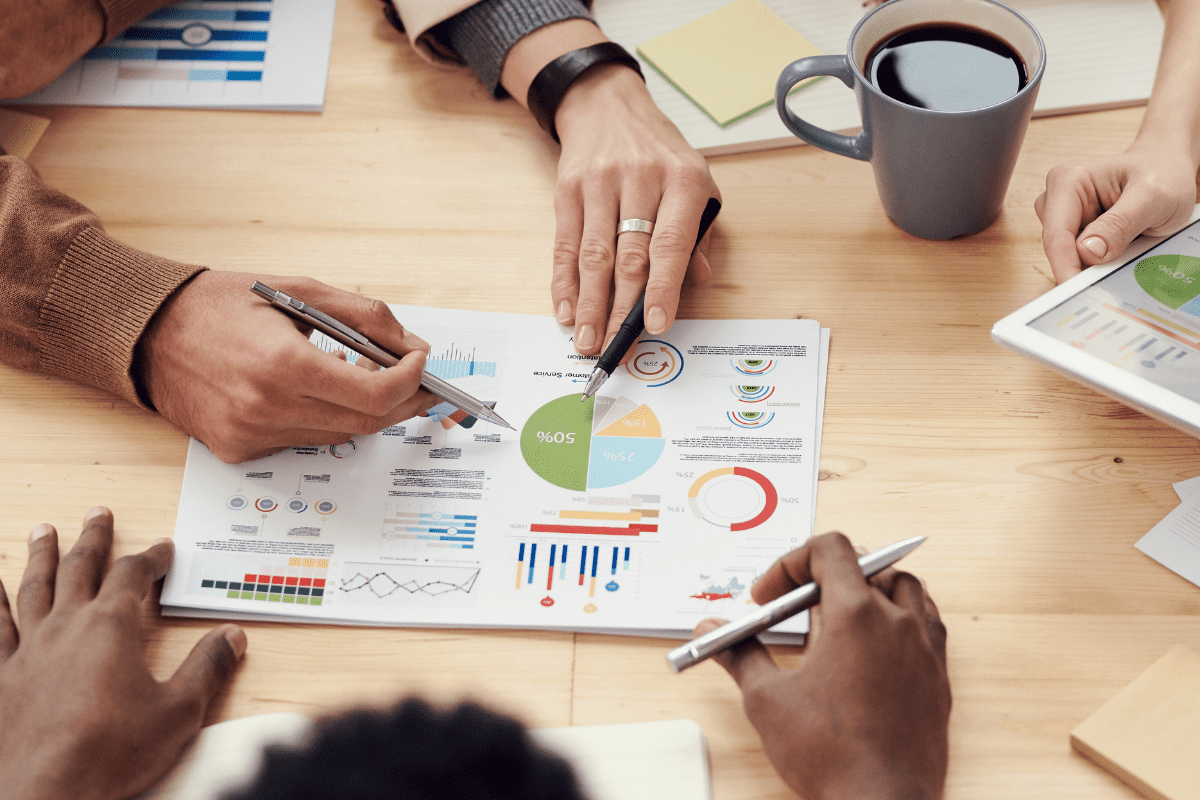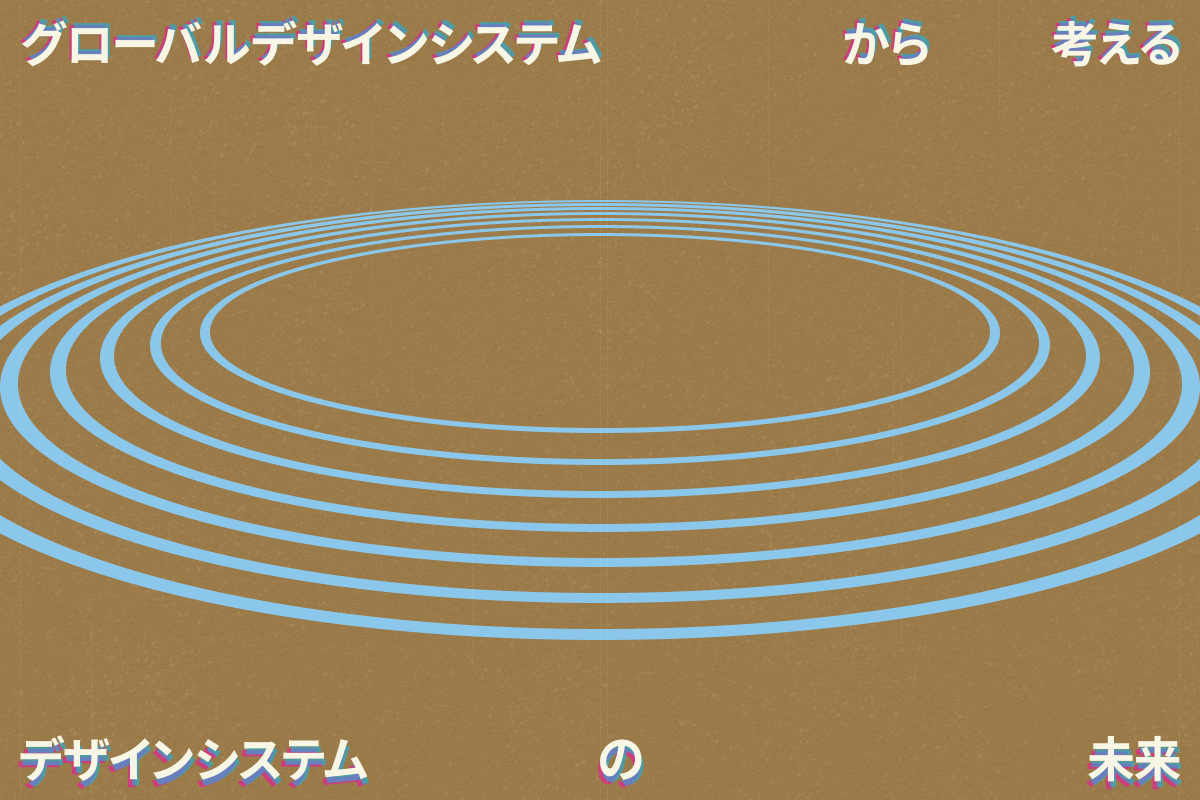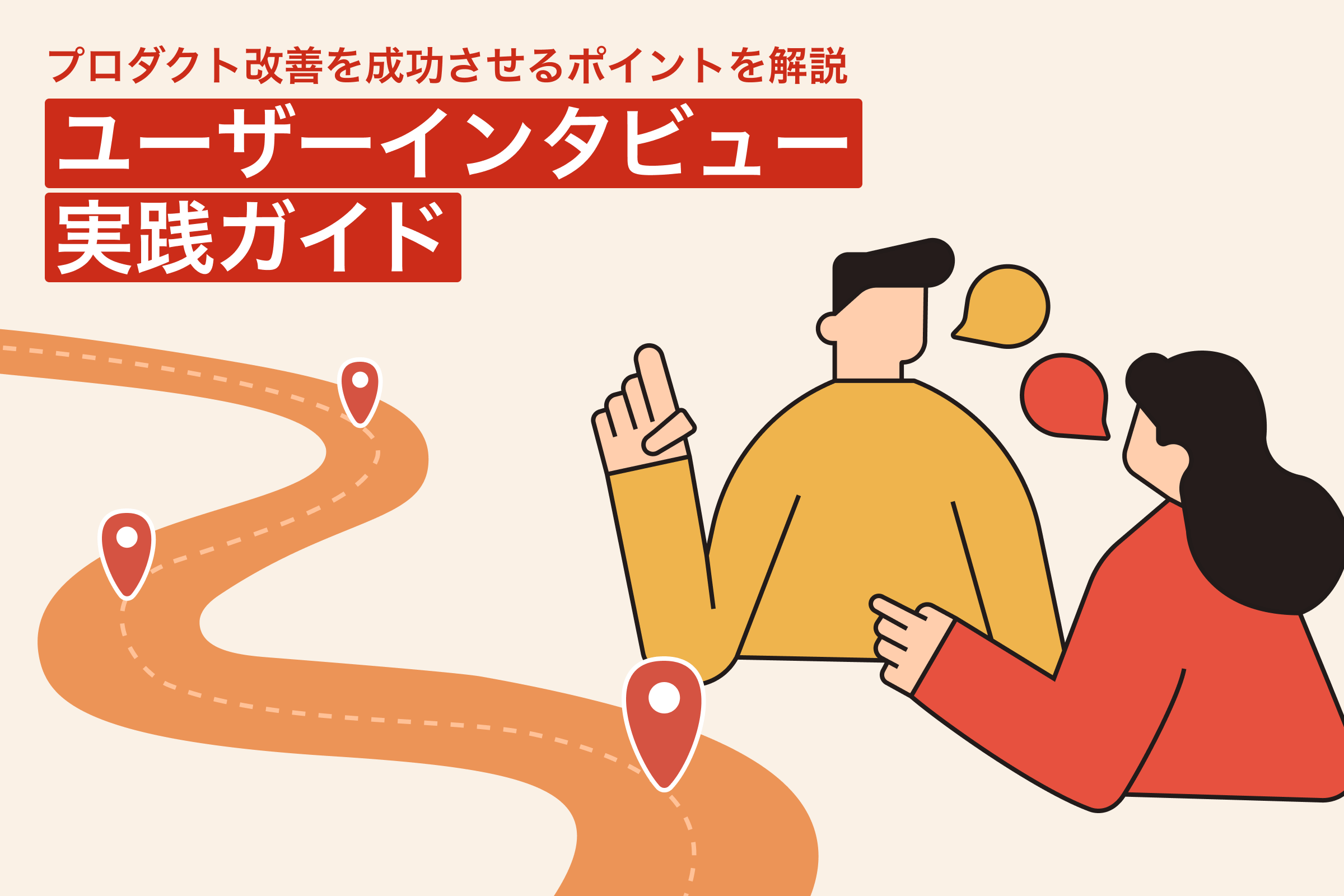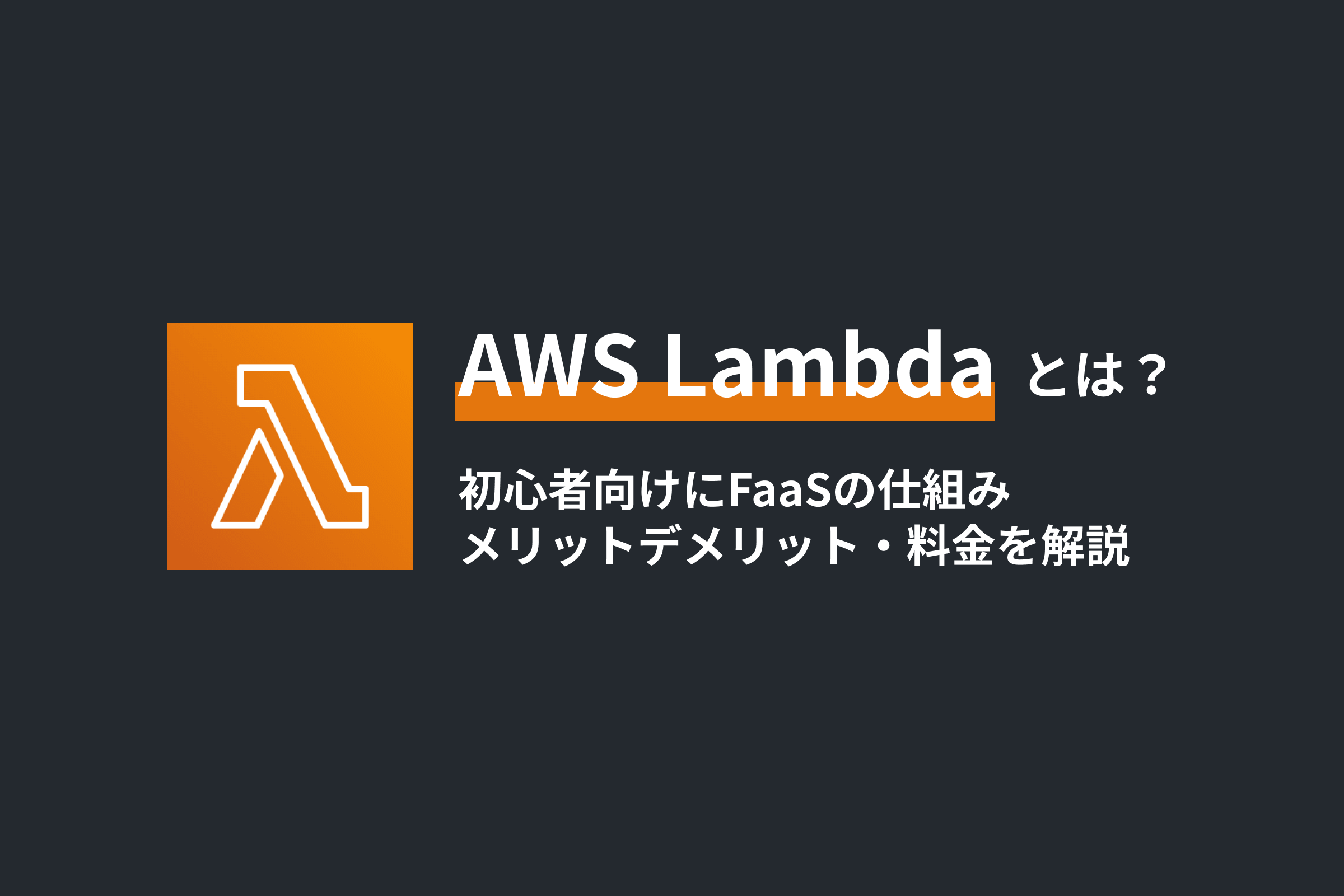デジタルトランスフォーメーションの潮流が勢いを増しつつあります。先日もアマゾンが音声サービスであるアレクサ部門だけで、新規に1147名を採用しようとしていることが明らかになりましたが、テクノロジーを巧みに活用して革新的な顧客経験を生み出そうとしている企業が、勢力を拡大し競争ルールを書き換えようとしています。この大きな変化の中で、これまでは強固な既存の収益基盤が邪魔をしてしまい、イノベーション活動の必要性が社内で十分に認知されていなかった企業においても、「新規事業を起こそう!」「イノベーションを生もう!」という大号令がトップから発せられ、各所で様々な取り組みがスタートしています。
しかし、立ち上がったプロジェクトのメンバーと会話をすると、「トップからダメ出しされたけど理由がよくわからない」「悪くないはずだが、なぜか次につながらない。」「これで良いのか確信が持てない。」といった声をよく聞きます。
それらの企業に共通していた根本的な要因としては2つが考えられます。
まず「自社にとってのイノベーションとは?」という共有化された定義が無いことです。次に、そのプロジェクトがどのような成果を目指すのかという、「プロジェクトの野心のレベル」が設定されていないことです。
この2つがチーム内で十分に話し合われていないことにより、議論の空転が続いていました。どこを目指すのか、どのようなプロセスを採用するのか、成功の基準は何か、についてチームで共通の認識が持てていなかったのです。
ということで、今日はイノベーションプロジェクトの「野心」の持ち方についてご紹介したいと思います。

<3つの野心レベル>
野心のレベル1:提供価値を磨きあげたい。
すでにマーケットにいる企業は、自社の製品の新鮮さと競争力を維持するために日常的に絶えず改良を行っています。具体的にはインタビューや観察といった方法から問題を発見し、それを良くするプロセスを用います。このアプローチは、顧客に新しいメリットをもたらします。自社が既にそのカテゴリーでのリーダーである場合、さらに有効です。一方で、改善した点が業界で認知されると、競合企業は素早く真似をするか対策を立ててしまうため、提供価値の優位性は通常長くは続きません。
野心のレベル2:価値提供の範囲を拡げたい。
それまで自社が提供していた製品・サービス価値の提供の範囲を超え、顧客のためにより包括的なソリューションを検討していくアプローチです。例えば、大手スポーツメーカのナイキは、より良いシューズづくりだけではなく、よりよいスポーツ体験をデザインすることでマーケットのリーダーの地位を維持しています。素材・美的感覚・機能面を越えてランナーの経験を拡げるイノベーションを生み出すことが、熾烈な競争を勝ち抜く要因となっています。
野心のレベル3:ゲームを変えたい。
これまで業界内で競争していた属性での競争をやめ、それ以外の属性で同時多発的にイノベーションを起こし、産業構造を根底から変えてしまうことを目指すものです。深い洞察が必要なだけでなく、プロジェクトオーナーの強烈な野心が欠かせません。例えば、アメリカ合衆国の航空機エンジンメーカーであるGEアビエーションは、元々この分野のリーディングカンパニーではありませんでした。しかしそこから、メンテナンス、資材管理、資産管理を統合したワンストップソリューションと、エンジンの稼働時間による課金方法を導入したことで、転機を迎えました。エンジン製造業から最適な運航を支援するコンサルティング業へとシフトし、航空機産業に今も革命を起こしています。
どのレベルについてもリスクやリターンがあるため、どれが正解か不正解かということもありません。ただ、これから始める取り組みはどの野心に沿うものなのかあらかじめ設定しておくだけで、メンバーの活動のベクトルが定まり、地に足のついた議論をすすめることができるように思います。
そしてプロジェクトのオーナー側(企業側)はそれぞれのイノベーション活動をポートフォリオで管理し、自社のイノベーション定義や成功基準と合わせてフィードバックしていくことが求められます。
プロジェクト立上げ時には是非とも、今回のプロジェクトでどのようなゴールを目指すのか?という「野心」について話し合ってみてください。
[contact]